君による、君のための実験ショー
ショー部門
ブース部門
実験ショー&ブース紹介
はじめに
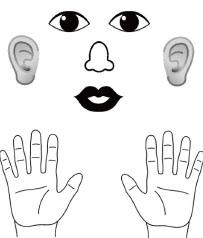 君が見ているもの。それは、いつでも真実であると自信を持って言えますか?
君が見ているもの。それは、いつでも真実であると自信を持って言えますか?
君が聞く音。あらゆる音の中で、なぜ、その音が君の意識に届いたのでしょうか?
君が触れるもの。それは君にどのような情報を与えてくれますか?
君が嗅ぐ、その匂い。君の感情や記憶にどのように結びつくでしょうか?
君が味わう時、その“おいしさ”は、いつでも同じでしょうか?
私たちが、「生きる」ことは、「感じる」こと。
私たちは、自分が今いる空間・状況で得られる様々な情報をキャッチして、正しく、時に“都合良く”処理して、生命を維持しているのです。そして、これらの処理をすべて引き受けているのが、脳です。
私たちの感覚と脳の関係を、ちょっとだけのぞいてみましょう!
今日、私が実験することは何もありません。
実験は、みなさん自身が行うからです。
私は、みなさんが行う実験をナビゲートします。
さあ、準備はいいですか?
ショーの時間では、みなさんの目から入る情報を、脳がどのように処理するのかを確かめます。
私たちは、見たものを一瞬のうちに判断しているのですから、難しいことは何もありません。
いつも通り見ればいいのです。そこに、君がとらえている世界の本当の姿を知る手掛かりが見つかるはずです。
ブース体験の時間では、みなさんの「聴覚(聞く)」、「触覚(触る)」を研ぎ澄ましてください。
注意深く感覚を働かせれば、私たちの感覚がいかに精巧かを実感することができるはずです。それなのに、時に感覚はだまされることもあります。「錯覚」の不思議を体験すると、わかっていても、正しく判断できない“変な感覚”が、意外とクセになるかもしれません。
また、私たちの目は、構造上、ものを見ることができない部分があることを知っていますか?それを確認することができます。
「君は、今日、新しい自分自身に出会えるはずです!」
実験ショー&ブースのポイント
私たちは、主に、目、耳、鼻、舌、皮膚の「五官」で自分に対する外部の刺激を受け、「感覚」が生じます。それぞれの感覚が、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚であり、これらを「五感」と呼びます。
感覚情報を脳が処理して、『眩しい』『うるさい』『くさい』『甘い』『痛い』といった自覚的な体験となるのが知覚であり、自分に対する外部の刺激が意味付けされます。知覚をもとにして、さらに『これは○○である』というように、それを解釈したり理解したりする過程や情報処理のプロセスが認知です。
ヒトの感覚は「五感」だけではありません。“かゆみ”などのように、その仕組みが未解明の感覚もありますし、無意識に働くと考えられている勘や直感、霊感、インスピレーションなどの「第六感」と呼ばれる不思議な能力を持つとも言われています。特に「直感」は、心理学や脳科学の分野で注目されています。
今回のテーマは、「自分自身を科学する」こと
私たちは、自分をとりまく世界からの刺激を感じて反応する自分の身体があるからこそ、「自分というもの」を確かな存在として意識できるのだと考えます。その意識を裏付ける感覚情報の精度と“あやふやさ”に迫るプレゼンテーションを試みます。私たちが、何かを判断したり、何かを信じたりする術とする「感覚」のしくみと、その感覚を司る「脳」の働きを、自分自身を通して知ることができる実験です。
“生きている”自分自身のメカニズムを、実感を伴って理解することで、自分自身の中にある、不思議と驚きの科学の世界を発見しましょう!
プロフィール

氏名:矢野 礼美(やの れみ)
所属:多摩六都科学館
大学では心理学を専攻。日本における生涯学習のあり方の研究に取り組み、学芸員、社会教育士、教員などの資格を取得して、人々の学びを支援する場である、多摩六都科学館の現職に就く。これまでに、館内、館外で行う科学普及事業の企画立案、実演を数多く担当。特にサイエンスショーの企画立案、実演の経験多数。幼児向け「キッズサイエンスショー」、学校団体向け「たまろく実験ショー」、館外出張授業にあたる「出前サイエンスショー」なども実演。また、多摩六都科学館を広く知ってもらうために、テレビ出演や、雑誌取材でサイエンスショーを実施。
自分の学んできた知識の特性を活かして、あらゆる視点からのアプローチを試みながら、私自身が感じた科学の「?」や「!」を、科学が好きな人だけではなく、科学に興味が持てなかったり、苦手と思っている人とも共感できるよう、日々活動中。

